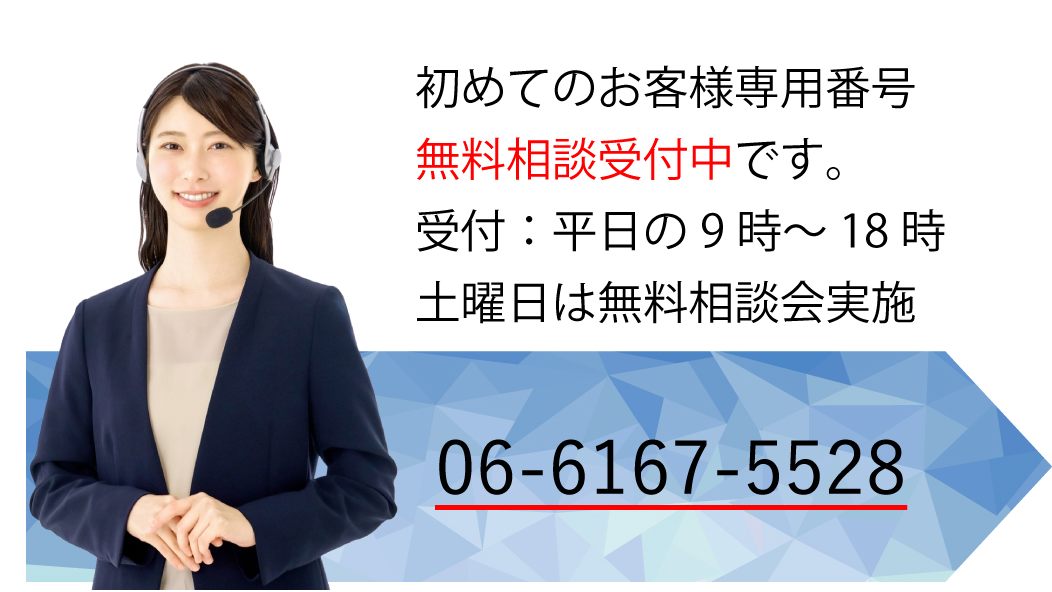相続手続きは遺言書を探すところから

この記事は遺言書の探し方について。
相続手続きで最初に行うのは、遺言書を見つけることです。
最初にエンディングノートが無いか探します。
故人がエンディングノートを書いていたら、そこに遺言書の事が書いてある可能性が高いです。
遺言書があるのと無いのでは、後に続く工程が大きく異なります。
参考までに相続手続きの流れを模した図を掲載します。

この図をご覧になると、相続人同士の話し合いや各種調査を省略できます。
漫画、遺言書の探し方

遺言書の探す方法をマンガにまとめました。
最低限の情報は上記にまとめております。
ここからは漫画で書いた情報をもう少し掘り下げた内容をご紹介します。
民法上には相続で使用できる遺言書が網羅されております。
実務上で使われる遺言書は以下の3つが中心になります。
- 公正証書遺言
- 法務局保管の自筆証書遺言
- 自己管理の自筆証遺言
公正証書遺言は、文字通り公正証書になった遺言書です。
公証役場で作成します。
自筆証書遺言は、故人(被相続人)が自分で書いたものです。
法務局保管と自分で管理するタイプに分かれます。
遺言書は複数あること珍しくない
遺言書の探す時の注意点ですが、1通見つけた後も調査を続ける必要があります。
故人が書いていた遺言書が1通とは限らないからです。
民法で遺言書は、一番新しい日付のものを正式な遺言書とするとあります。
(要件を満たしている事が前提ですが)
例えば公証役場で保管されていた遺言書が見つかった後で、法務局で保管していた遺言書。
もしくは仏壇から自筆証書の遺言書が見つかった…
この様な事例は珍しくないです。
遺言書を定期的に書き直す人は意外とおられます。
(横溝正史氏の犬神家の一族や山崎豊子氏の女系家族みたいな極端なのは少ないですが…)
2通3通と出てくることは普通にあります。
相続が終わった後で新しい遺言が見つかると、トラブルの元になります。
公証役場で見つかった場合でも仏壇や金庫などにも無いか確認が大事です。
公正証書遺言の探し方

公正証書遺言の探し方を紹介します。
手順は以下の通りです。
- 近くの公証役場を探す
- 公証役場に遺言書の有無を確認(検索)
- 保管されている公証役場に謄本を交付請求
近くの公証役場を探す。
公証役場は日本全国にあります。
最初の段階は近くの役場で大丈夫です。
探しかたは公証人連合会のサイトに一覧があります。
https://www.koshonin.gr.jp/list
例えば行政書士やまだ事務所の最寄りの公証役場ですと。
梅田公証役場になります。
梅田の場外馬券売り場があった近くのビルです。
(梅田駅から少し離れるので便が良いとは言い切れない)
公正証書遺言の有無を確認
連絡する公証役場が分かりましたら。
故人が作成した公正証書遺言があるか確認します。
公証役場には公正証書遺言等登録検索システムが備え付けられています。
システムを使って、遺言書があるかを確認します。
検索は故人の利害関係人(相続人)や代理人(行政書士など)のみ可能です。
利害関係者であることを証明する書面の提出が必要です。
・申請書
・故人(被相続人)の除籍謄本(死亡事実あり)
・関係者の戸籍謄本(故人との繋がりがあること)
・関係者の印鑑証明書
・関係者の実印
・関係者の本人確認書類(免許証など)
・委任状(行政書士等が照会するとき)
これらを提出後、公証役場が調査をおこないます。
その結果、公正証書遺言がある場合は、交付に必要な情報をもらうことができます。
(公証役場の場所や作成年月日、作成した公証人の名前など)
昭和63年以前の公正証書遺言について
公証役場の公正証書遺言等登録検索システムですが、登録されているものは昭和64年1月1日からになります。
昭和63年12月31日より前の公正証書遺言は、公証役場の保管庫に保管されております。
何が言いたいかと言うと、システムで検索できないので、心当たりの公証役場を1件1件確認する必要があります。
被相続人(故人)の戸籍の附表を参考に所在地を管轄する公証役場を片っ端から…
想像以上に骨の折れる作業になります。
公正証書遺言の謄本の交付請求
公正証書遺言があることが分かった時は、謄本を請求します。
今度は保管されている公証役場に行います。
原則は保管された役場に来訪して請求になります。
平成31年からは郵送での請求も可能になりました。
請求前に公証役場に電話連絡が必要です。
公正証書遺言の謄本請求にも必要な書類があります。
・故人の除籍謄本(死亡事実あり)
・故人との関係が分かる戸籍謄本
・印鑑登録証明書
・実印
・免許証など本人確認書類
・手数料(1ページ250円)
・委任状(行政書士など)
法務局保管の自筆証書遺言の探し方

次は法務局保管の自筆証書遺言の探し方について。
2022年から法務局で自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
紛失や偽造改ざんのリスクを防ぐため、事前チェックで使えない遺言書を減らすことが目的です。
大変便利なサービスです。
弊所も自筆証書遺言作成のご依頼は、法務局保管をご案内しております。
法務局保管の自筆証書遺言の探し方
- 死亡時通知が届いた
- 法務局で保管されているか確認
自筆証書遺言の死亡時通知とは
①の死亡時通知は、法務局から遺言書が保管されていることを通知してくれるサービスです。
遺言書を保管する時に通知者を設定している場合に通知が来ます。
(最大3名まで設定可能)
大抵は故人の相続人に通知が届くように設定していると思います。
法務局から通知が届いた場合は、保管された遺言書があることが判明します。
次は法務局で遺言情報証明書を発行してもらいます。
この証明書が遺言書の代わりになります。
(銀行などに提出することが可能)
法務局に保管されているか確認
法務局からの通知が来ない時は、
- 法務局保管された遺言書が存在しない
- 通知の設定が無い。
どちらかになります。
この時は本当に法務局に遺言書が無いか調べる必要があります。
確認できる人は、相続関係人(相続人、受遺者、遺言執行者)です。
(行政書士、司法書士などの代理人は確認できない形になっています。)
遺言書の確認は、どこの法務局でも対応可能です。
例えば弊所でしたら、大阪の谷町4丁目駅近くにある大阪法務局(本局)に行きます。
窓口に行くときは、事前予約が必要です。
もしくは郵送でも請求可能です。
窓口で以下の書類を提出します。
・申請書
・遺言者(故人)の戸籍・除籍謄本
・関係者の戸籍謄本
・請求者の住民票の写し
・免許証など写真付きの本人確認書類
・その他
郵送の場合は後日に遺言書保管事実証明書が発行されます。
法務局で遺言書情報証明書を申請
死亡時通知、遺言書保管事実証明書で保管されていることが分かった時。
次は遺言書のデータを入手します。
(原本は交付されないことに注意)
遺言書のデータは、遺言書情報証明書と呼ばれる紙になります。
この証明書で銀行や証券会社などで遺言書として使えます。
(普通の自筆証書より喜ばれるかもです)
遺言書情報証明書は何処の法務局でも請求可能です。
(行政書士や司法書士等は請求できません)
必要書類は保管通知ありと無しで分かれます。
・申請書
・請求者の住民票
・戸籍謄本
・顔写真付きの身分証明書
・返信用封筒(郵送希望の場合)
・通知書
次は保管通知なしの場合です。
・申請書
・法定相続情報一覧図の写し
(作成している場合)
・一覧図が無い場合
・遺言者(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票の写し
・切手つきの封筒(郵送希望の場合)
この場合は故人と相続人全員の戸籍謄本が必要になります。
実質的に相続人調査を行うことになります。
必要書類を提出後、数日後に法務局に取りに来る。
もしくは郵送で送られてきます。
.png)
証明書一枚とるために、
故人と相続人全員の戸籍がいるのか…
思ったより大変だねぇ。
.png)
戸籍の取り寄せや相続人調査を行政書士に依頼することできます。
大変ですので、良かったら弊所にご相談くださいね。
自宅で保管している自筆証書遺言の探し方

ラストは自宅で保管している遺言書の探し方を紹介します。
自宅で管理している遺言書は、公正証書遺言の謄本と自作の自筆証書遺言の2種類あります。
自宅以外だと親族や専門家(行政書士等)や親しい知人が預かっている場合もあります。
まずは親族に預かっていないかを確認します。
預かっている場合は、自筆の場合は開封しないで家庭裁判所で検認手続きを行います。
公証役場や法務局に連絡と同時並行で、自宅を探すことになります。
(財産調査と一緒に行うことが多いです。)
余談ですが、銀行の貸金庫に保管されてる時は厄介です。
相続人全員の印鑑証明や戸籍が必要になります。
もしこれから遺言書を作成する方は、貸金庫以外の場所に保管することをお勧めします。
自筆証書遺言は開封厳禁です
自宅保管の遺言書での注意点ですが…
自作の遺言書は見つけても開封は止めておきましょう。
相続人にとっては、非常に関心の高い情報であるので、直ぐに見たい衝動にかられると思います。
下手に開封してしまうと、後々でトラブルの原因になります。
(改ざんや処分してしまうリスク)
自筆証書遺言は家庭裁判所の検認という手続きが必要です。
家裁で封を切って、中身を確認します。
故人の自宅を探す
まずは遺言者(故人)の自宅を探してゆきます。
今までの経験で保管されていることが多い場所は以下の通りです。
- 仏壇の引き出し
- 箪笥の上の引き出し
- 机の引き出しの中
- 自宅金庫の中
まずはこの辺りを重点的に調べます。
大抵は封筒に入れてあるかと思います。
遺言書が封されている場合ですが…
直ぐには開封はNGです。
家庭裁判所での開封と確認手続きを経てから中身確認になります。
エンディングノートに書かれている場合もあります。
故人が終活を行っていた場合、高確率でエンディングノートを作成していると思います。
エンディングノートが見つかった時は、そこに遺言書の在処が書かれている場合も。
前にあった話ですが、本棚の本の中に挟んであったことも…
相続が始まる前に偶然に見つけられたので助かりました。
(相続完了後に見つかったらトラブルのリスク)
専門家が保管している
専門家(行政書士など)が保管している場合もあります。
自宅をくまなく探しても遺言書が見つからなかった時。
お付き合いのある税理士さんなどが居られましたら、遺言書を預かっていないか確認しましょう。
もしくは遺言書は見つからなかったけど、専門家の名刺やパンフレット、郵便物などがあった時。
専門家が預かっていることがあります。
法務局の保管制度が始まる前は、事務所の金庫に保管されることが一般的でした。
彼らが出入りしていた痕跡が見られたときは、名刺などに載っている連絡先に電話してみましょう。
他にも遺言書が残っていないか確認
遺言書が見つかった後、捜索を続ける事もあります。
理由は被相続人が複数の遺言書を作っている時があります。
ミステリーやサスペンスでは、大抵複数の遺言が出てくるものです。
(横溝正史の犬神家の一族みたいに矛盾する遺言が何通で出てきたら困りものですが)
遺言書に有効期限は有りませんが、書き直した時は新しい遺言が有効になります。
ここまで遺言書の探し方をご紹介して参りました。
調査方法としては網羅されていると思います。
以上が遺言書の探し方を漫画で紹介するでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
【大阪府行政書士会より表彰】
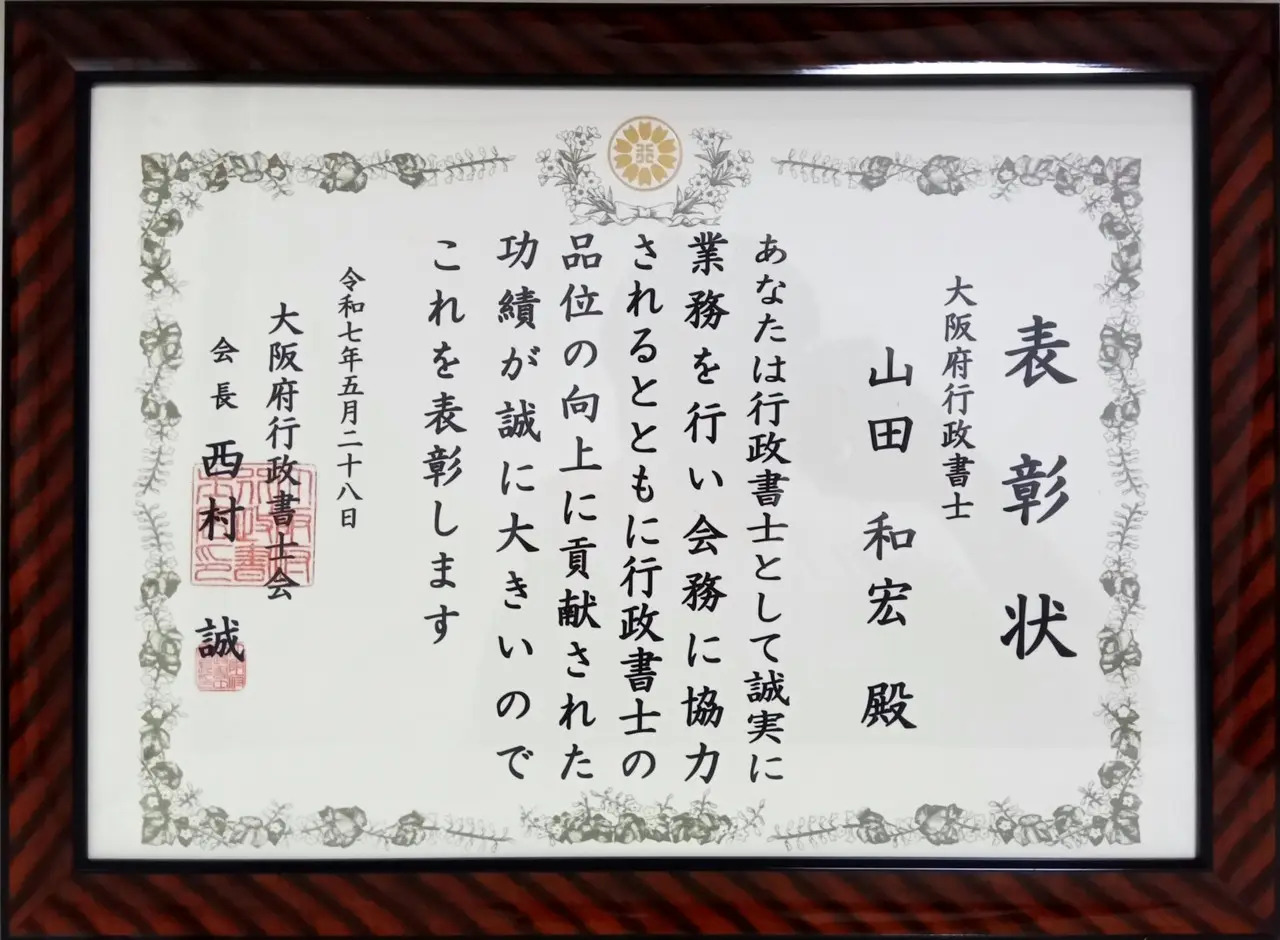
【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所の個人情報の取り扱いとサイト記事に関する免責事項について
【運営サイト】