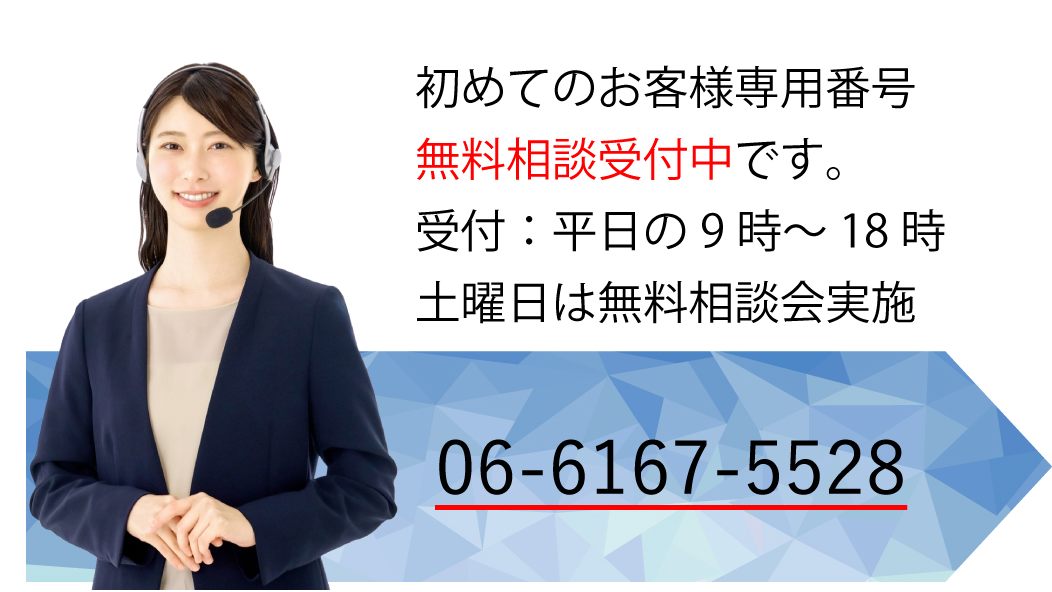マンガ、任意後見を検討する時

この記事は任意後見についてザックリと全体像をご紹介します。
細かい論点は別記事で解説を予定しております。
親族が重度の認知症などになった場合、本人の支払いも銀行口座も動かせなくなります。
(口座がロックされて途方に暮れることに…)
その時に銀行員や施設の職員、社会福祉協議会など役所の職員から、
「ご親族に後見人をつけてください」
この様に言われます。
主治医やケアマネジャーの方、専門職(法律職)と協力して、色々な書類を集めて家庭裁判所に申し立て。
後見人候補には、親族の面倒を見てきた自分を候補にしましたが…
専任されたのは面識のない専門家…
この様な話をニュースで見ることが多くなりました。
(同時に後見人の横領事件なども…)
最近は最高裁で親族後見人もという話が出てきていますが…
現状、法定後見の7割以上は弁護士や司法書士、社会福祉士など専門職後見人です。
万が一の後見人ですが、前もって選んでおけば…
自分がシッカリしている内に、信頼できる後見人を選ぶことが可能です。
事前に後見人を選べるのが、任意後見という制度になります。
任意後見に関する注意点をおいておきます。
(この部分を知らないと後見人等と問題になることがあります)
後見人は本人の財産保護と生活を守るための制度であり、被後見人の親族が財産をコントロールする為の制度ではありません。
この部分は法定後見、任意後見のいずれも同じです。
任意後見とは

ここから任意後見について解説して参ります。
少し専門用語が多くなります。
任意後見について箇条書きにすると以下の様になります。
- 本人が契約を単独でできる判断能力がある内に
- 将来の老齢、病気、怪我等により判断能力が不十分になった時に備えて
- 本人が希望する人に
- 本人の財産管理などの代理権を与える契約を行う
任意後見は法定後見と異なり契約書(公正証書)を作成して行います。
(任意後見に関する法律で定められております。)
また任意後見は3つの選択肢があります。
どのタイプがベストかは状況によりますが、選択肢があることを知っておくと全然違います。
任意後見人ができること・できないこと
任意後見での代理権の内容は多岐に渡ります。
本人の生活や療養看護、財産管理に関する全部の事務です。
例えば病院や施設の入所や退院、銀行口座からお金を引き出しや年金などの受領。
本人が保有する不動産の売却(家庭裁判所の許可が必要)などが後見人が行えるようになります。
後見は本人のありとあらゆる権利を行使できる訳ではありません。
以下の様なものは、任意後見の対象外となっています。
- 契約に定めていない項目
- 本人の婚姻や離婚、養子縁組など身分行為
- 医療行為や臓器移植など、本人の承諾が必要な行為
- 強制を伴う行為(引っ越しや病院や施設への入院を強制)
- 介護などの事実行為(別の契約や専門職の領分)
- 本人がした契約への取消権と同意権
任意後見制度は契約に基づき本人の意思が尊重されます。
そのため本人が行った契約への取消や同意を任意後見人は行えません。
取消権が必要な場合は成年後見制度(法定後見)が必要です。
任意後見制度のメリット

次に任意後見のメリデメを紹介します。
任意後見は法定後見にない長所がありますが、同時にデメリットもございます。
メリットは以下の様なものがあります。
- 自分が頼みたい人にお願いできる
- 判断力が低下する前に色々と決められる
- 代理権の範囲を契約で決められる
- 後見契約の開始時期を決められる
- 任意後見が始まる前からサポートを受けられる
任意後見で一番の利点は、自分が頼みたい人にお願いできる点です。
色々相談していた専門家(行政書士など)や面倒を見てもらっている親族など。
次に後見人ができる範囲を話し合いで決めることができること。
例えば重要な財産の処分は相続で行いたいので、後見段階で触れない様にするなど。
これらの事柄を頭がシッカリしている内に、親族や専門家と擦り合わせながら決めることができます。
法定後見だと判断能力が厳しい段階で、親族や役所(市町村の職権)で手続きが進みます。
また終活支援に行政書士などの専門家がお手伝いしている時は、任意後見の前から継続的なサポートを受けられます。
例えば、見守り契約で定期的なコミュニケーションを取ったり、生前事務委任契約を結んで本人の代わりに支払いを代行したり等。
また任意後見の終了後に死後事務や相続のサポートなどもございます。
任意後見のデメリット
任意後見は短所もあります。
箇条書きにすると以下の様な物がデメリットとして挙げられます。
- 任意後見が開始する時の手続きが大変
- 後見人の他に監督人が必要になる
- 監督人の報酬が発生する
- 一度後見を始めると解約が難しい
まず任意後見契約は契約書を交わしただけでは効力がありません。
家庭裁判所で任意後見の手続きを行う必要があります。
手続きには関係者との面接や家裁調査官の調査、本人の判断の能力について医師の診断などが必要です。
手続き開始から後見が始まるまでの間、時間がかかります。
(その間は後見人候補者も親族も代理権が存在しない)
次に任意後見契約を始める時には、後見監督人が付されます。
監督人は後見人のサポートや監査を行う人です。
監督人になる人は、弁護士や司法書士などの司法関連の専門職です。
(ちなみに弁護士や司法書士など専門職であっても監督人が付されます。)
一度、後見監督人が付されると彼らに報酬が発生します。
月額で1万円~3万円程度の費用が発生します。
後見が何年にも渡ると、かなりの額になります。
お金が掛る反面、彼らの知識やノウハウを活用することも可能。
(ある種のアドバイザーと思えば高くないかも…専門職の人件費は想像以上に高額です)
法定後見にも言える話ですが、
一度後見を始めると、本人が亡くなるまで外すことは出来ないです。
(後見人の交代はあり得ますが、後任の後見人が付されます)
相続で遺産分割協議書にサインが欲しい、不動産を売却したいからスポットで後見したい…
この様な場合でも、亡くなるまで後見が続きます。
まとめ
本人の判断能力に疑いが出始めた時、銀行や役所、介護などの関係者から後見人を求められます。
法定後見だと、本人や親族が希望する人ではなく面識の無い専門家が後見人になる事が多いです。
前もって任意後見契約を結んでおくと、信頼できる人に事務を任せることができます。
弊所でも任意後見など終活のお手伝いをしております。
終活のサポートが必要な方は、お気軽にお問い合わせください。
ご遠慮は無用です。
以上が任意後見とはについてザックリと解説でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
【大阪府行政書士会より表彰】
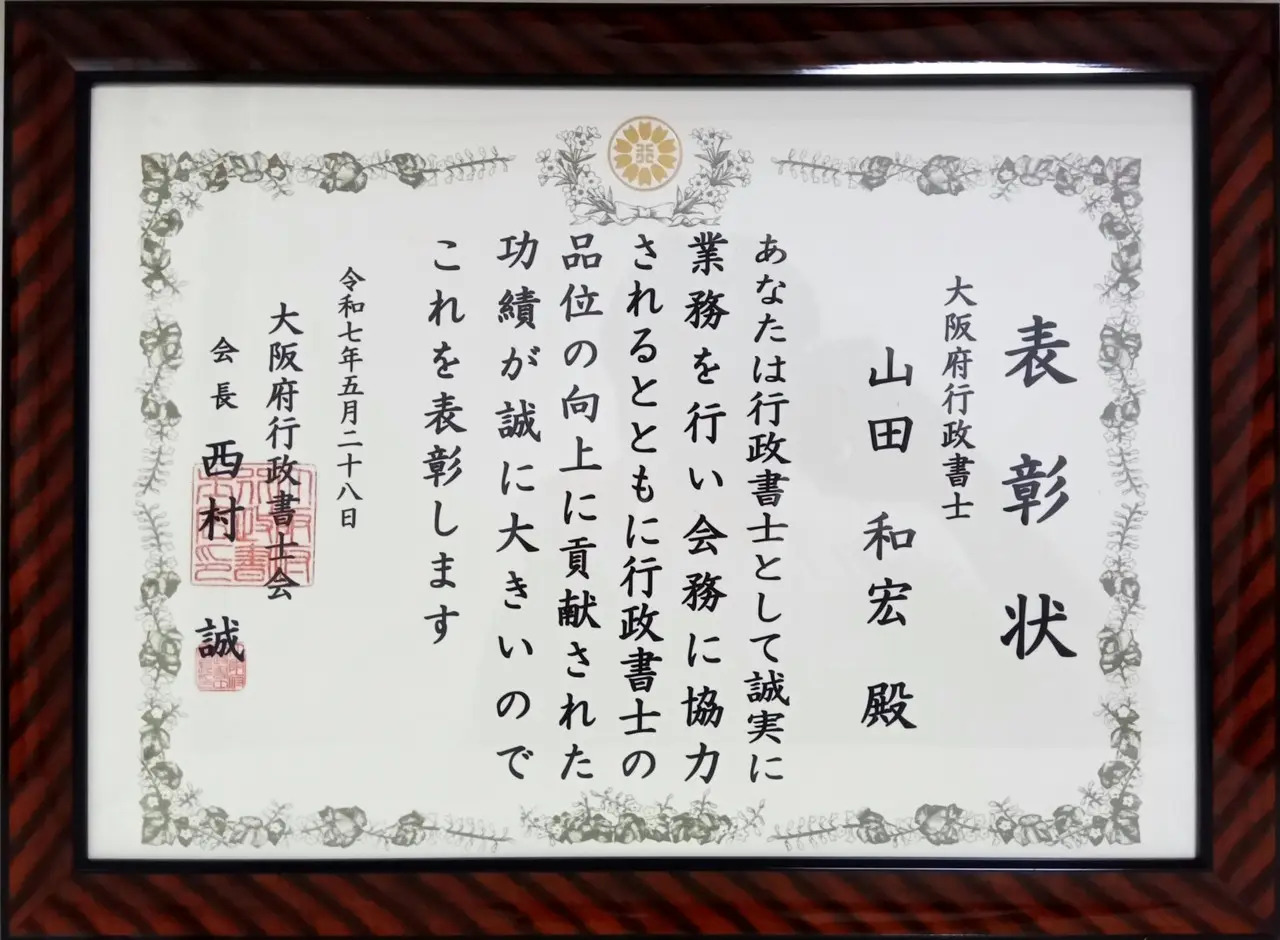
【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所の個人情報の取り扱いとサイト記事に関する免責事項について
【運営サイト】