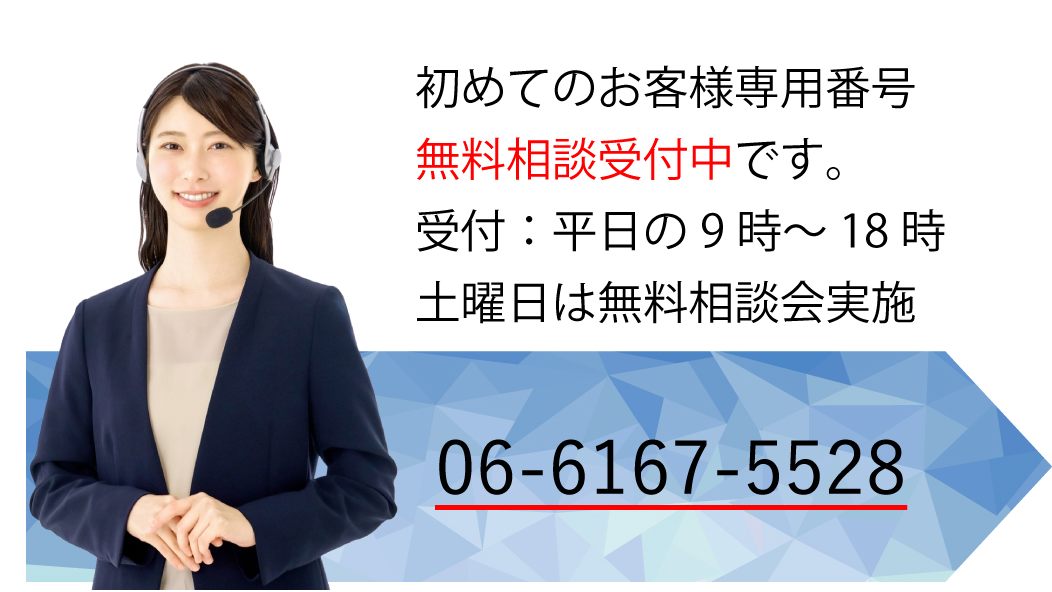マンガ、任意後見とは

この記事は任意後見の取消権について解説します。
任意後見契約では、本人の契約に対する取消権がありません。
任意後見で取消権が無い理由などをこの記事ではご紹介していきます。
まずはマンガを使って任意後見について簡単に解説します。
任意後見の全体像は別記事で詳しく解説しております。
任意後見について箇条書きにすると以下の様になります。
任意後見制度の最大の特徴は、本人が後見人を選ぶことが出来ることができます。
- 本人が契約を単独でできる判断能力がある内に
- 将来の老齢、病気、怪我等により判断能力が不十分になった時に備えて
- 本人が希望する人に
- 本人の財産管理などの代理権を与える契約を行う
任意後見は法定後見と異なり契約書(公正証書)を作成して行います。
(任意後見に関する法律で定められております。)
契約の取消権とは
取消権とは法律行為が無効または取り消し可能である場合に、その行為を後から取消しにする権利です。
未成年者や成年被後見人の財産や権利を保護するために取消権は存在します。
未成年者や成年被後見人が不利益な契約を結んだ場合、その契約を取り消せる権利が法定代理人や成年後見人などに与えられています。
例えば成年被後見人(保護される人)が高級羽毛布団を買ったり、自宅のリフォーム契約や自宅不動産を売る契約を交わしたりした場合、成年後見人は被後見人がした契約を取り消すことができます。また成年後見人は本人(成年被後見人)がした契約を取り消すことが出来ますが、スーパー等で買った日用品や食品などの日常家事に関する契約は取消不可です。
これらの取消権は、成年後見契約(法定後見)では可能ですが、契約で行う任意後見では後見人に付けることが出来ないです。
任意後見人に取消権が無い理由について

任意後見人に取消権が無い理由は箇条書きにすると以下の様になります。
- 取消権は法定後見のみ付与される
- 本人の意思尊重が最優先
- 取消権の乱用リスクを防ぐため
取消権は法定後見(成年後見制度)
消権が認められるのは、原則として「法定後見」の場合です。
法定後見は家庭裁判所が成年後見人を選任し、本人の保護が目的となります。
成年被後見人の要件は、本人が判断能力を常に欠いている状態であり、不利益な契約を保護するための取消権が必要とされています。
常に欠いて居る状態とは、重度の認知症などで単独で日常生活も厳しい状況にあります。
別の言い方をすると、補佐は補助者が居れば理解できるですが、法定後見の場合は補助者が居ても契約の内容や契約することを理解することが難しい状況になります。
しかし任意後見では、契約に基づいて任意後見人が支援するだけであり、取消権を行使できる立場にはありません。
本人の意思尊重が最優先
意後見契約は、本人の意思を尊重することを基本理念としています。
根拠法、任意後見契約に関する法律第6条にもその旨が書かれています。
(本人の意思の尊重等)
第六条任意後見人は、第二条第一号に規定する委託に係る事務(以下「任意後見人の事務」という。)を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
引用:E-GOV法令検索、任意後見契約に関する法律
本人が信頼する相手に後見事務を委任する制度であるため、任意後見人は本人の意思に基づいて行動します。
取消権を認めてしまうと、本人の意思を過度に制限する可能性があり、制度の趣旨に反することになります。
取消権の濫用リスクを防ぐため
取消権が任意後見人に与えられると、不必要なトラブルや問題が発生する可能性があります。
特に取消権が濫用された場合には、本人や相手方に不利益をもたらす恐れがあります。
本人が納得して行った契約でも、任意後見人の思惑で取消された場合、本人に意思を尊重しているとは言えないです。
例えばとある支払いの為、本人が有価証券の売却や定期預金を解約したとします。
任意後見人が相続財産が減ることを恐れて、契約や売却や支払いを取り消したとします。
この様な場合、本人の意思を尊重せず、相手方にも大きな迷惑をかけることになります。
任意後見人は、本人が選んだ人が任意後見人になります。
後見人が本人より自分の利益を優先する人物だった時、任意後見の意味が無くなります。
(濫用リスクを防ぐために、家庭裁判所から後見監督人が付されますが…)
任意後見に取消権が無いことへの対応

任意後見人に取消権がない場合、本人やその家族は以下の対応方法を検討することができます。
方法は任意後見契約を結ぶ前と結んだ後で対応が変わります。
任意後見を結ぶ前
- 契約内容を事前に慎重に確認
任意後見契約を結ぶ前なら、本人の保護に最適か確認が必要です。
悪質商法などから守るのが目的の場合は、任意後見より成年後見制度が最適です。
もしくは後見まで至らないケースで保護が必要なら、補佐や補助を検討することも重要です。
補佐や補助にもメリット・デメリットがありますので、注意が必要です。
補佐や補助制度を付けてしまうと、相手方から取消しリスクを恐れられて敬遠されるリスクがあります。
任意後見契約を結んだ後
- 別の制度で取消権を行使する
- 法定後見に移行する
クーリングオフなどを活用
任意後見人には取消権や同意権がありません。
この場合は、別の法律や制度での取消権を行使できるか検討します。
代表的な制度としてはクーリングオフがあります。
クーリングオフで対応できるなら、それを行使して契約を取り消す形になります。
ただクーリングオフは契約から8日間など時間的な制約があり、行使が難しい部分があります。
法定後見制度に移行する
もう一つは任意後見契約から法定後見へ移行することです。
任意後見では保護しきれないと判断した時に使う手段になります。
(意外と法定後見に行くことが多い)
任意後見契約に関する法律にも移行する時の為の規則が設けられています。
(任意後見契約の解除)
第九条第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される前においては、本人又は任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除することができる。
2第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後においては、本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができる。
引用:E-GOV法令検索、任意後見契約に関する法律
任意後見契約に関する法律の第9条に解約に関する規定があります。
9条1項には契約発動前は、公正証書を使って任意後見契約をいつでも解除できる旨。
2項には後見発動後は、家庭裁判所の許可を得て解除できる旨が。
本人の保護に取消権が必要で、任意後見→法定後見に移行する場合は、正当な理由となる可能性が高いです。
まず専門家や家庭裁判所と相談して方針を決めるのが良いと思います。
以上が任意後見人に取消権が無い場合についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
【大阪府行政書士会より表彰】
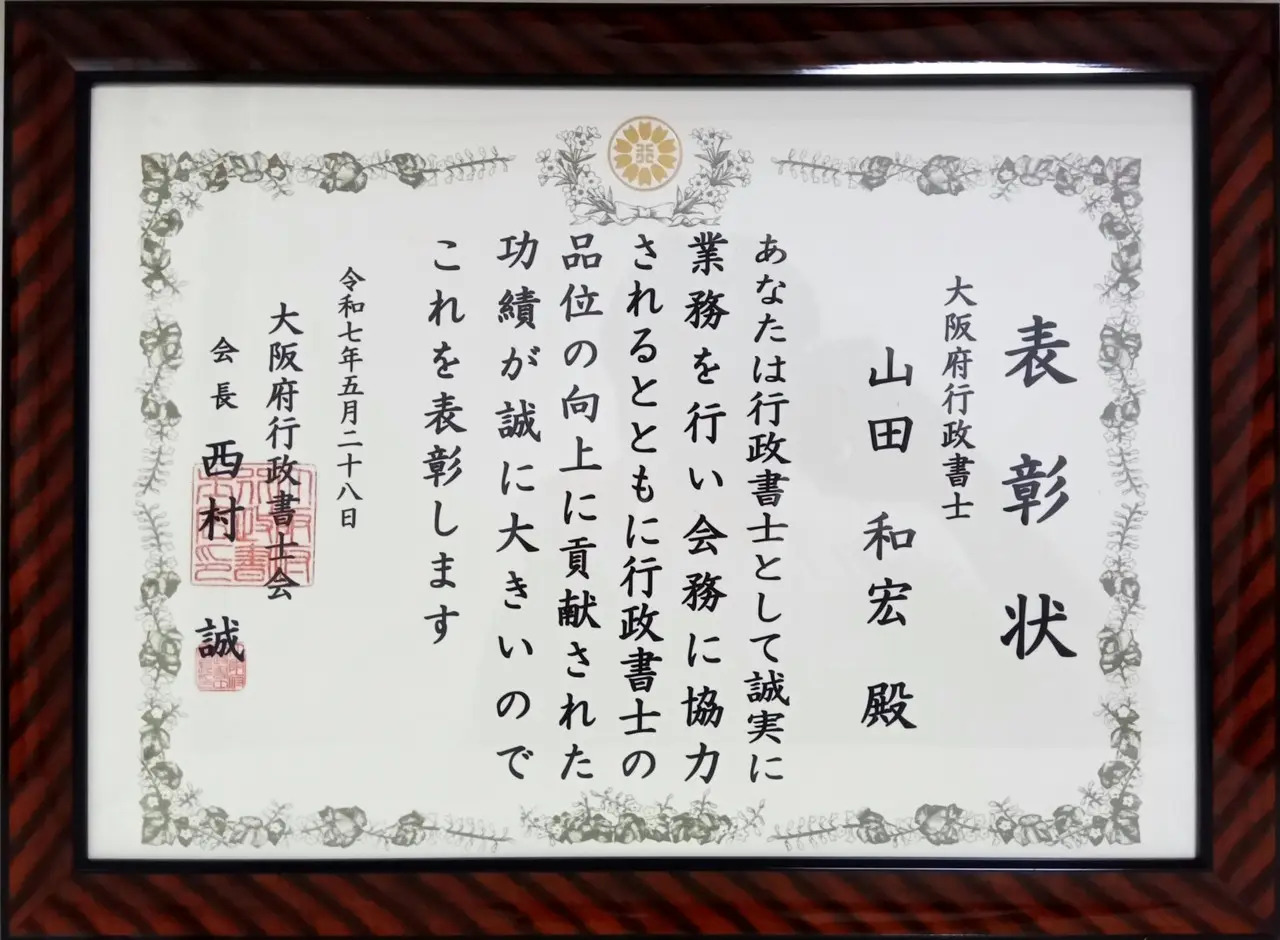
【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所の個人情報の取り扱いとサイト記事に関する免責事項について
【運営サイト】