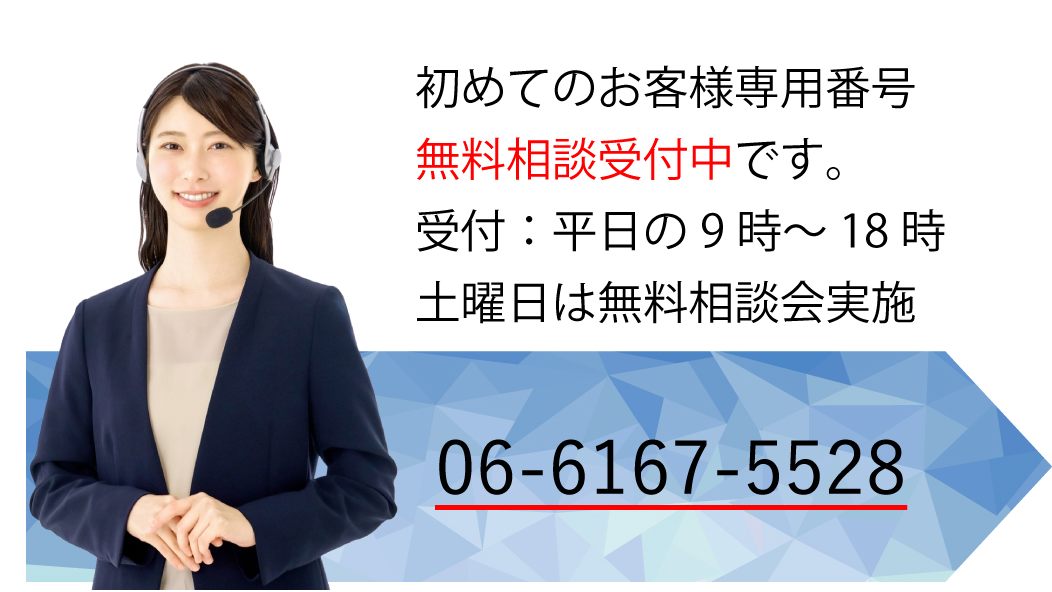任意後見とは自分の判断能力がシッカリしている内に将来の財産管理や事務管理の代理権を託す契約です。法定後見は自分で選んだ人が後見人になれない事がありますが、任意後見の場合は選んだ人が後見人になります。
大阪の相続手続き、遺言書作成は行政書士やまだ事務所へ
漫画、任意後見について解説

この記事は任意後見の流れについて解説して参ります。
まずはマンガを使って任意後見について簡単に解説します。
任意後見の全体像は別記事で詳しく解説しております。
関連記事:任意後見制度について
任意後見について箇条書きにすると以下の様になります。
任意後見制度の最大の特徴は、本人が後見人を選ぶことが出来ることができます。
- 本人が契約を単独でできる判断能力がある内に
- 将来の老齢、病気、怪我等により判断能力が不十分になった時に備えて
- 本人が希望する人に
- 本人の財産管理などの代理権を与える契約を行う
任意後見は法定後見と異なり契約書(公正証書)を作成して行います。
(任意後見に関する法律で定められております。)
また任意後見は3つの選択肢があります。
どのタイプがベストかは状況によりますが、選択肢があることを知っておくと全然違います。
関連記事:任意後見は将来型・即効型・移行型の3種類あり
任意後見に関する注意点をおいておきます。
(この部分を知らないと後で、後見人等と問題になることがあります)
後見人は本人の財産保護と生活を守るための制度であり、被後見人の親族が財産をコントロールする為の制度ではありません。
また後見人が考える財産保護と親族が考える財産保護に食い違いが発生する可能性がございます。
この部分は法定後見、任意後見のいずれも同じです。
任意後見契約の流れ

任意後見契約は法定後見と異なり契約書に基づいて行われます。
本人と契約書を交わしただけでは効力はございません。
後見が必要な時が来た時に家庭裁判所で手続きが必要です。
家庭裁判所を挟む理由は、後見契約で付与される権限が非常に大きくなるためです。
被後見人(本人)の口座やクレジットカード、権利証などを預かり財産管理を行います。
契約書だけで簡単に後見契約が成立すると、色々と問題や犯罪が発生するリスクが高いものです。
そのため任意後見契約は法律で厳格に要件や手続きが定められております。
任意後見契約が始まるまでの流れ

任意後見契約は大きく7つのステップに分かれます。
さらに細かく分けると16ステップになります。
- なぜ任意後見が必要なのか?
- 誰が後見人になるのか?
- 契約書の原案作成
- 公証役場で公正証書作成
- 法務局に後見登記
- 家庭裁判所で後見監督人の選定
- 後見業務の開始
ここからは上記のステップを一つづつ解説してゆきます。
なぜ任意後見が必要か
最初に本人に任意後見が必要なのかを考えます。基本的に任意後見は、本人の将来の財産管理や生活を維持するために行います。
任意後見以外に方法が無いのか?等を検討します。
例えば本人がアパート経営している場合、先の未来に判断能力の衰えで不動産管理ができなくなる恐れがあります。
この様な場合ですが、任意後見では難しい部分があります。
任意後見では不動産の最低限の保全くらいしかできません。
本人の代わりに大家業を十全に行うためには、任意後見ではなく家族信託の方が適している部分があります。
任意後見人の選任
任意後見契約を進めることを決めた後は、誰が被後見人(本人)の後見人になるかです。任意後見のメリットは後見人を選べることです。
後見人は契約書を作成する時には、決めておく必要があります。
任意後見人の候補者としては以下の方が挙げられます。
- 親族
- 事実婚パートナー
- 友人知人
- 専門家(行政書士など)
- 法人(後見業務を扱う法人)
最初に検討するのは、本人と近しい親族になると思います。
(法定後見は親族が難しいから任意を選ぶケースが多い)
親族の場合、専門家などに支払う報酬が発生しません。
報酬は遺産相続で後払いみたいな感じになります。
(監督人への報酬は別途必要)
その代わり、自分が色々と動く必要が出てきます。
または同性婚や事実婚のパートナーのケースもあります。
現在の民法では同性婚は認められていません。
パートナーの生活や財産管理を考える場合、任意後見が必要になるケースが多いです。
専門家や法人の場合、任意後見が始まると報酬が発生します。
財産内容にも依りますが、月額2万円~5万円。
(月額5万とかは数千万単位の貯金がある場合など)
その代わり大変な後見業務を任せることが可能です。
関連記事:任意後見人は誰がなれる?
任意後見契約の原案を検討
任意後見人候補が決まったら、契約書の原案を考えます。特に権限をどの程度まで持たせるのかは重要です。
(法定後見と異なり契約の取り消し権はない)
文案については、任意後見の書籍やインターネットでもヒットします。
専門家を入れない場合は、ザックリとした文書で良いと思います。
(正式な文面は公証人と打ち合わせで作成します)
個人的には行政書士などの専門家と一緒に考えることをお勧めします。
ポジショントークではなく、法律や任意後見のルールに不案内な状態で文案を考えるのは大変です。
(どれだけ頑張っても抜けや漏れ、付与できない内容が含まれます)
専門家と話し合うなかで、最適な任意後見契約の原案ができると思います。
また終活に関する色々なアドバイスが貰えます。
(任意後見だけでは、本人のサポートは万全とは言えないです)
専門家を後見人にする必要はありません。
関連記事:死後事務委任について
関連記事:見守り契約について
公証役場で任意後見の公正証書作成
ある程度、原案ができたら公証役場に連絡を取ります。公証役場には管轄があり、都道府県内の役場になります。
弊所だと梅田や本町の公証役場に行くことが多いです。
まずは原案を公証人に送り、チェックしてもらいます。
その後に公証人と話し合いながら、契約書の文言を作っていきます。
原案が完成したら、本人と後見人が一緒に公証役場に行きます。
この時に印鑑や印鑑証明、免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類を持参します。
(公証役場からアナウンスあり)
作成前に公証人が本人確認と意思確認を行います。
本当に自分の意思で任意後見契約を作成するのか?
本人は契約の内容を理解しているのか?
ここで本人に作成の意思なしと判断されれば、そこで終了になります。
本人の意思確認が完了したら、契約書を作成します。
PCで作成された原案をプリントアウト。
プリントアウトされた文書を公証人が読み上げます。
それを聞いて間違いが無いか、修正点が無いかなど確認します。
文案に問題なければ、書面にサインします。
サインが終われば、原本は公証役場、正本と謄本は本人と後見人候補者に渡されます。
法務局に登記
契約書作成後、公証人が東京法務局に任意後見の内容を登記します。法務局にある登記ファイルに、本人の代理権の内容などが記録されます。
登記ファイルに登録されると、登記されていないことの証明書に任意後見した旨が記載されます。
家庭裁判所での手続き
任意後見は契約書作成から発動するまでに時間がかかります。(使う前に亡くなる方もいらっしゃいます)
後見人を選ぶ際は、本人と年齢が近い方は避けた方が良いかもです。
(本人より先に亡くなる可能性もゼロではない)
契約後も判断能力が衰えるまでは、普通に生活ができます。
判断力に疑いが出始めた時に、家庭裁判所で手続きを開始します。
申し立てができるのは、4親等以内の親族、任意後見受任者です。
まず家庭裁判所に必要な書類を提出します。
書類受理後、家裁が調査や面接、医師の診断などを行っていきます。
その後に後見監督人が選任されます。
後見監督人とは、後見人のアドバイザー兼、監督者になります。
監督人は弁護士か司法書士など司法分野の専門家が就任します。
任意後見の場合、必ず監督人が付きます。
監督人の就任後から契約が効力を発揮します。
同時に支払いがスタートします。
関連記事:任意後見人の報酬
次に東京法務局の登記ファイルに後見開始の旨が記録されます。
手続き終了後、後見人と監督人に登記事項証明書が交付されます。
ここから後見業務が始まります。
以上が後見検討から開始までの流れでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
この記事を書いた人

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
【大阪府行政書士会より表彰】
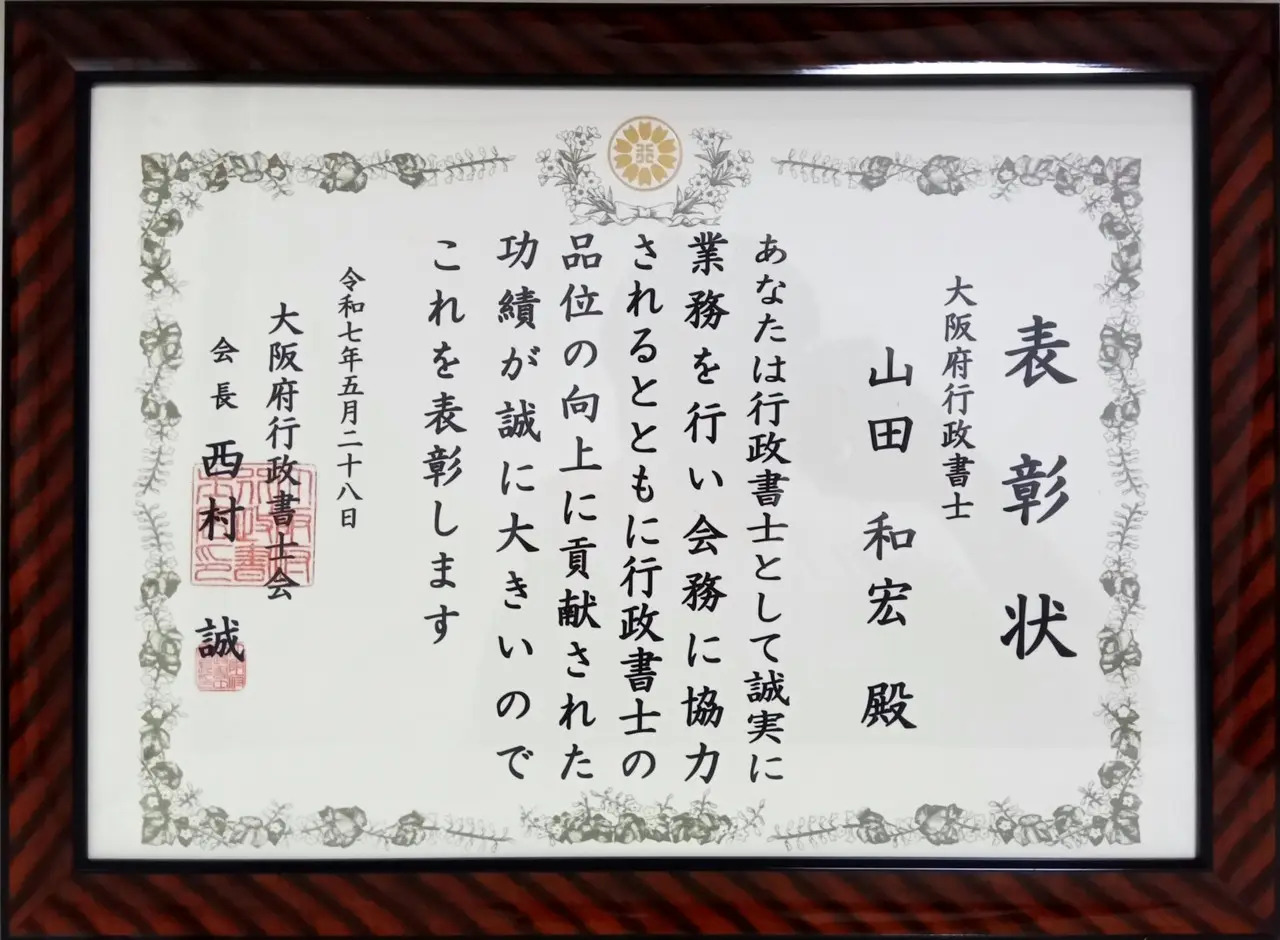
【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所の個人情報の取り扱いとサイト記事に関する免責事項について
【運営サイト】